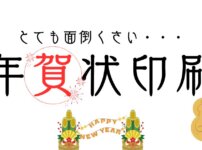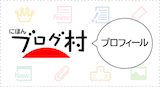お月見とは・・・

【お月見】ってなんだかわかりますか?
【旧暦】っていうのも関係している。
正直・・・全然わかりません・・・。


日本に定着している【お月見】そのルーツを説明します❗
そもそも【月見】は・・・平安時代・・・
貴族から始まった【宮廷行事】でした。

さらにその歴史は、中国【中秋節】から来ています。【旧暦】についても説明しますね❗
楽しみです❗❗

ニュースなどで【旧正月】とか【旧暦】とか
聞いたことありませんか?
聞いたことあります❗旧暦に中国人がお祝いしたりしてますよね?


そうそう❗現在、アジアの多くが【旧暦】を使っています。
日本はその文化が入り、
明治5年までこの【旧暦】を使った。
そして・・・
1873年(明治6年)1月1日から現在の
【新暦】を使い始めています。
5月は皐月(さつき)7月は文月(ふみづき)
とか言いますね?これは【旧暦】の読み方。
更にいうと・・・
旧暦=月の満ち欠けで1ヶ月を測る。
(=太陰暦)
新暦=地球が太陽の周りを1周するのを測る。
(=太陽暦)

上の画像は「29個」の月があります。
このように月の形を見て、日にちを決める。
これが【旧暦】

29日で1ヶ月。つまり29×12ヶ月=1年は348日。
ほら、もうずれましたね?我々の使う
新暦は・・・1年365日。ズレは1年で17日。

なので、いろいろとお祝いごとに「ズレ」が生じているわけ。
なるほど・・・そういうことか❗


1年で17日ずれてはヤバいので、現在の旧暦は太陽暦も取り入れているので、誤差は少しだけ。
この誤差を埋めるのが「うるう年」です。
中秋の名月とは・・・?

なぜ【中秋】というのか・・・
先ほど説明した「旧暦」では
1.2.3月 ⇨ 春
4.5.6月 ⇨ 夏
7.8.9月 ⇨ 秋
10.11.12月 ⇨ 冬
としています。
なるほど❗これ、「古文」とかで勉強しました❗そういうことか❗

【中秋】とは「秋の真ん中」つまり・・・
7.8.9月の秋の真ん中「8月」(=中秋)
15日(十五夜)頃に「月が綺麗に見える」
中国ではこの中秋にお供物をして
「親族の幸せを願った。」
これが日本に伝わり、日本では貴族たちが
毎月15日頃に宴をするようになった。
伝来したものを全国民に周知させるのは
難しいことなので・・・まずは貴族で。

中国の【中秋節】では「月餅」が出される。それが伝わり、日本では「餅」を食べるように・・・。
あ・・・そういえば、十五夜といえば・・・「うさぎ」ですよね?なぜうさぎなんですか?

これも日本が平安時代に導入した
「仏教」がきっかけです。
⇩ 仏教について ⇩
-

-
仏教宗派はわかりにくい!そんな仏教の教えや仏教とはをわかりやすく解説!仏教伝来の歴史を学ぶ。
世界三大宗教の一つ「仏教」。なぜ仏像を作り出したのか、その始まりはなんと【インド】です。過去を学ぶことで、今を知ることができる。
続きを見る
⇩ 仏教伝来時代の歴史は ⇩
-
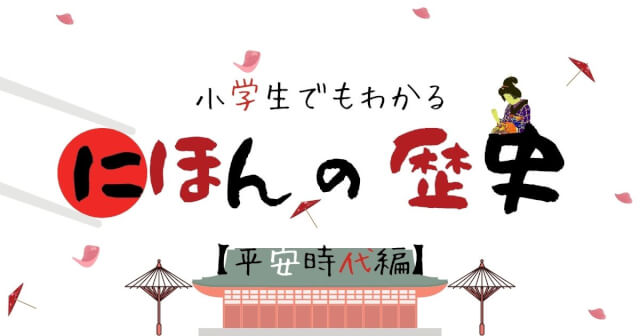
-
わかりやすい歴史!日本の歴史簡単にわかりやすく解説!日本史年表で流れを学ぶ!日本の歴史漫画も紹介。【平安時代】
「歴史を改めて勉強したい人」も「歴史が苦手な人」も「歴史が好きな人」も読むだけで歴史が好きなり、今すぐにでも紹介したくなること間違いなし!
続きを見る
これは仏教国インドの物語です・・・
「昔、ウサギと猿とキツネがいました。
ある日、食べ物が無く、困っていた老人に
3匹は出会いました・・・。
3匹の動物は老人を可哀想に思い・・・
猿は木で木のみをとり、キツネは川で魚を。
しかし、ウサギは食べ物を手に入れることは
できなかった・・・。
悩んだウサギは「私を食べてください。」と
火に飛び込み、死んでしまった。
この老人が実は神様の化身で、ウサギを想い
月で蘇らせてくれた。ウサギはそこで
生き返らせてくれた老人のため
餅を必死についたそうな・・・。」
これがずっと【言い伝え】として
残っているのです。
お月見で楽しむ【中秋の名月】

お月見・中秋の名月・旧暦
おわかりいただけたでしょうか?
月が綺麗だなぁ・・・
と愛の告白をした人がいるように
月は多くの人の幸せを願ってきました。
ほら、ウサギがお餅をついてます。
ヨーロッパの人は女性の横顔に
見えるのかな?
今日はここまで・・・。