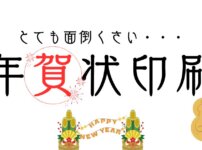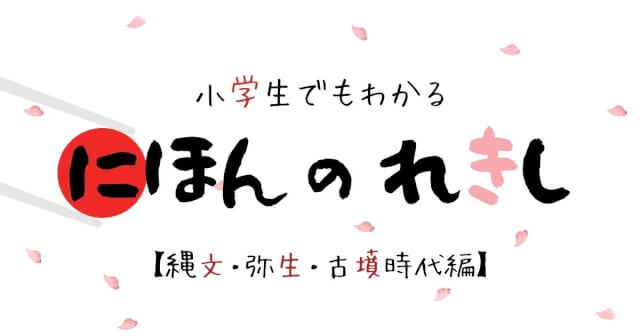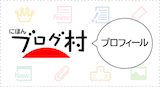歴史を学びたい人・歴史が苦手な人
歴史が好きな人・たまたま来た人。笑
この記事では【流れ】を重視し【わかりやすく】を
1番に日本の歴史を解説していきます❗
そもそも日本はどのように誕生したのか。
それが記されている『古事記』の記事が
この歴史記事の前章になります。
⇩ 日本誕生史はこちら ⇩
-
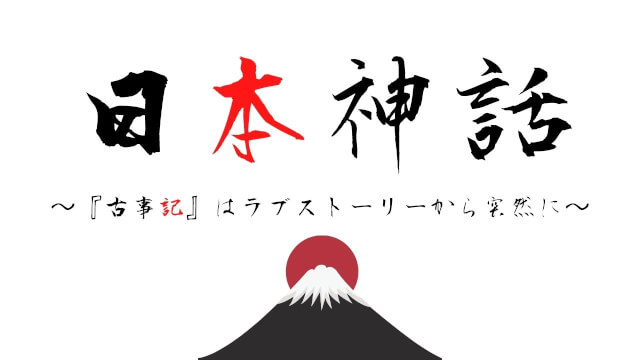
-
日本の歴史わかりやすく解説!日本の歴史を簡単に学べるのはここ。日本史わかりやすく勉強。古事記わかりやすく学ぶ。
日本の歴史を知りたい人、苦手だけど楽しく勉強したい人など読むだけで流れがわかる日本史記事です。一緒に楽しみましょう!
続きを見る
日本の歴史簡単にわかりやすく解説!

縄文時代よりも前、日本は長きにわたる
【旧石器時代】が存在していた。
農業もなく、木のみや魚を採集。石ヤリを使い、
猟もしていた。同じ場所で狩りをすると獲物が
いなくなってしまうので・・・

家も季節によって移動できる簡易的なものでした。
この旧石器時代から縄文時代までは10.000年の
歴史がある。
い、いちまんねん!!?

そのため使用する道具も進化をしました。
採取したものをより長く安全に保管するため
【土器】を発明し、縄をつかい紋様(もよう)を
つけ、分別した。これが【縄文土器】。

「縄」で「紋様(もんよう)」を使用していた「縄文時代」がくる。
わかりやすい歴史【縄文時代の到来】

旧石器時代のあとの縄文時代は争いはほとんどなく
人口もまだまだ少なかった・・・。
朝起きて、腹減ったら狩りをして、食べて・・・
遊んで・・・寝る・・・その繰り返し。
めちゃくちゃいいですね❗食っちゃ寝食っちゃ寝・・・


これが「狩猟文化」。川で魚をとり、陸では動物を狩り、木の実や草を採る。
土器も発明したことで、採集物の保存期間が格段に
長くなったため移動生活はせず、同じ場所での生活
が始まることになります。
「竪穴式住居」ってやつですね?中学でやりました❗



川では魚やタコ、ハマグリなども。陸ではシカやイノシシ。大人数での狩りではクマを相手にしたことも。
ちなみに、当時の男性の平均身長は158センチ
女性の平均身長は148センチで平均寿命は15歳。
若っ❗❗

貧富の差もほとんどなく弥生時代へ・・・。
わかりやすい歴史【弥生時代へ】

この時代に大きく変わったのが「稲作」。
「水耕」が中国から伝来したこと。

お隣中国はすでに【始皇帝の時代】。日本はゆったりしていますね。
⇩ 始皇帝の面白秘話 ⇩
-

-
【世界史の窓】超わかる!中国歴史人物「始皇帝」中国歴史ドラマや中国歴史書でもおなじみ〜わかりやすい年表〜
「キングダム」では吉沢亮演じる役がこの【始皇帝】中国4000年の歴史の中で世界で初めて巨大帝国の国家に君臨した男。始皇帝のおもしろ秘話。
続きを見る
もちろん「稲作」が伝わっても狩りはします。
基本は自給自足生活。畑の移動はできませんので
田んぼを作った【農地に定住】した。
土器も、より高度に、より薄く、よりきれいに。
【定住】をしたことで食べ物の収穫は安定し
人口もどんどん増え、より多くの米を収穫する
ため、地域同士で協力し【集落】ができます。
「ムラ」の誕生です。
おぉ〜❗❗繋がりますね❗


「狩り」は難しく、運もある。体調不良だといけないし・・・。
ただ「農業」は豊作・不作が自然と発生します。
「稲作伝来」が「光」だとするならば、「闇」は
「貧富の差の発生」です。
気温も、環境も、天気も農地ごとに違いますもんね・・・。

そして、豊地にある「貯蔵物」を奪い合う「争い」
つまり「戦争」が始まるのも弥生時代。
各集落は他の集落に攻撃されないよう集落の周りに
「濠(ほり)」をつくりました。これが「環濠集落」
といわれるもの。

「お堀(ほり)・濠」は「溝(みぞ)」のこと。周りを水で囲んでいるお城とかありますね?あれが濠(ほり)です。
この定住は各地に広がり、ムラは増え、ムラ同士が
協力し、巨大化し「クニ」となる。こうした
【小さなクニ】があちこちに成立、小国乱立時代へ
突入する・・・。
わかりやすい歴史【小国乱立時代】

小国乱立があったことがなぜわかったかというと
中国の文献に書かれていたから。
小国乱立時代に頭角を現した「国」があり
それが【邪馬台国(やまたいこく) 】。
あ!卑弥呼ですね❗


そうです❗そうです❗
当時の中国は「魏」という王朝で、魏はこの日本を
「倭」と呼び、どんな国なのか魏の書物に記した。

実はこの書物には「魏」から「倭」の「距離」と「方角」が書かれています。
現代の研究者がその道標をたどると・・・
どうしても「太平洋」をさしてしまう。
ということは・・・間違っている?


そう。「魏」の書物の「距離」か「方角」のどちらかが間違っている。
もし・・・距離があってて「方角」が違うのなら
邪馬台国は「九州」に存在していたことに。
方角ではなく「距離」が間違っているのならば
邪馬台国は「近畿」に存在したことに・・・。

どちらなのかは今も解明されていない【謎】なのです・・・。
さて、話を戻しましょう。
卑弥呼には「壱与(いよ)」という娘がいました。
壱与は、中国「魏」のあとに成立した「晋」に
使者を送りますが・・・晋はすぐに「分裂時代」へ。
邪馬台国の情報も途絶えてしまった。
その情報がない中、日本に「ある現象」が起きた。
それが「古墳の乱立」です。

「乱立」なので、乱立する地域に巨大な政権があったということ。
学校でも聞いたことがある「大和政権」
大和政権は本当に実在したのか・・・
存在した場所は九州なのか、それとも近畿か・・・
この古墳時代からはとてもなぞめいた時代であり
資料も少ない。だから日本の古代史を学ぶと
「よくわからなくなってしまう」。

でも流れをしっかり押さえれば大丈夫❗
もう面白いです❗「時代は流れている」のがわかります。

ついに日本はこの古墳時代を乗り越え・・・
歴史が本格的に始まろうとしていました。
飛鳥の地で日本の歴史がついに動き出す❗
⇩ 続きの物語はコチラからw ⇩
-
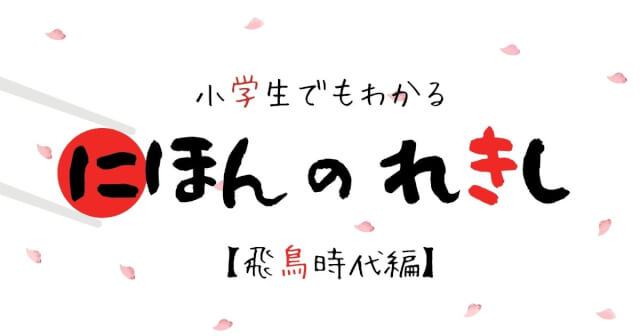
-
わかりやすい歴史!日本の歴史簡単にわかりやすく解説!日本史年表で流れを学ぶ!日本の歴史漫画も紹介。【古墳〜飛鳥時代】
「歴史を改めて勉強したい人」も「歴史が苦手な人」も「歴史が好きな人」も読むだけで歴史が好きなり、今すぐにでも紹介したくなること間違いなし!
続きを見る